一連の記事で「アンペアブレーカー」と何度も連呼していますが、
そもそもアンペアブレーカーって何なの? とピンときていない人もいるかと思います。
逆に、「アンペアブレーカーはアンペアブレーカーだろ」と思っている人は、
「って何なの?」と言われても、意味が分からないかもしれません。
じつはアンペアブレーカーは、住んでいる地域(管轄の電力会社)によって呼び名が
違ったり、そもそもアンペアブレーカーが設置されていなかったり、
と地域差があるものなんです。
地域差というのは大きく2つ。
電気料金のプランが、アンペア制か、最低料金制か、という違いです。
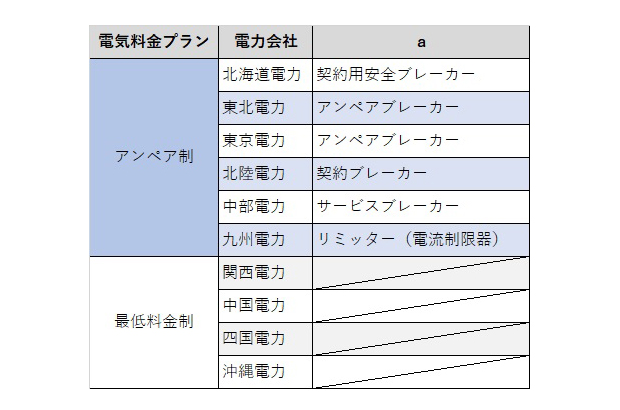
最低料金制の地域には、分電盤にアンペアブレーカーがありません。ただ、場所や目的ごとに個々のブレーカーは付いています。なので、「ブレーカーが落ちる」という経験はどの家庭でもしていると思います
まずは「アンペア制」。
これは、電気を使い始めるときに「わが家は何アンペアまで使うか」という上限を
住み手が決めて電力会社と契約するものです。
うちは30Aとか、40Aとか。そういう契約です。
なので、契約の上限を超えて電気を使うと、
アンペアブレーカーが落ちて停電、という流れになるのでした。
「契約で決めた以上の電気を使わないように!」という電力会社からのメッセージ・・・
ではなく、引込線などの太さによって流せる電気の量が決まっているため、
安全のためブレーカーが落ちる、というわけです。
「最低料金制」のほうは、電気を使っても使わなくても、
あらかじめ支払う最低料金が決まっているという契約です。
この契約をしている家の分電盤にはアンペアブレーカーがありません。
「アンペアブレーカーって何なの?」という人は、そういうプランを採用している
電力会社がある地域に住んでいる人だと思います。
では、最低料金制の地域には、使用する電気に上限がないのかといえば、
あります。
一般家庭などでは60Aまでが上限です(アンペア制の地域も60Aまでです)。
一般的な住宅なら60Aもあれば十分ですが、
「ウチは二世帯住宅だし、エアコンや床暖や、そのほか家電がいっぱいあるので
60A以上使いたい」という家庭、あるいは店舗などは「従量電灯」ではなく、
その上位ランクの「低圧電力」の契約をします。
ちなみに、「アンペア制」の地域は、契約アンペア数に応じて基本料金が変わり、
アンペア数が多いほど基本料金も高くなります。
アンペア制も最低料金制も、電気を使えば使うほど料金を多く払わなければならないのは、
どちらの地域も同じです。
















