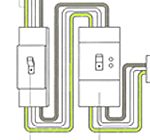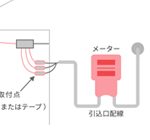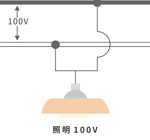古民家の天井を見上げると、梁にポツポツと白いお猪口みたいなものが
付いていることがあります。
古い世代の方はご存じでしょうが、それは「がいし」です。
漢字で書くと「碍子」。
昔の屋内配線の方式で、碍子を利用した配線を「碍子引き配線」といいます。

古民家でよく見かける「碍子引き配線」。思わず触りたくなるサイズ感とかたちです。これは土間の大黒柱にくっつけてあるので異様に目立ちます(笑)。この配線は念のため数年前からブレーカーを落しているそうですが通電させればまだ普通に使えるそうです
碍子は何のためにあるのかというと、電気配線が漏電を起こさないようにするためです。
その昔、電線を覆っていたのは布でした。
電線に麻や綿などの布を巻いて蝋〈ロウ〉を染み込ませたもの(蝋引き)を
使用していました。
現在の電線はビニールで被覆されていますが、当時は布ですから絶縁性が悪く、
そのまま梁の下などに這わせてしまうと配線が漏電を起こして火災などの
原因になったのです。
そこで、電線を建物から浮かせて配線するために利用したのが碍子でした。
「碍」という漢字はほかではあまり見かけませんが、「妨げる」とか「邪魔をする」
という意味です。
磁器で出来ているので絶縁性はばっちりです。

黒く煤けているうえに小さいので分かりにくいですが、碍子を相互につなぐように電線が張ってあります
碍子引き配線は昭和20年代の建物ではよく見かけますが、
昭和40年代以降の建物になると急に見なくなります。
おそらく昭和30年代に現在のケーブルによる屋内配線方式に切り換わったのでしょう。
古民家を改修するとき、碍子引き配線をそのまま利用することはまずありません。
基本的には現在の配線方式でやり替えます。
しかし、
近ごろは古民家のレトロな雰囲気に合わせて、あえて「古い碍子引き配線」を
「新しい碍子引き配線」にやり換えることがあります。
とくに、インテリアにこだわる古民家カフェなどでよくやられています。
新しい碍子引きについては、回をあらためてお話しします。

移築した古民家。梁は煤けていますが配線は黒くなっていません。昔の電線は赤っぽい色をしていますが当時の規格なのかもしれません。ちなみに、右端にぶら下がっている電球の黒色のケーブルは現代の新しいものです