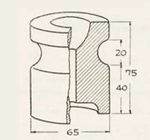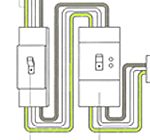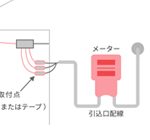瓦屋根の補修をしている土蔵を見かけたので、ちょっと見学させていただきました。
瓦屋根の一番上の部分を「棟」あるいは「大棟」といいます。
棟を高く積んで立派に見せるのが昔からのやり方で、
瓦職人はそこで大いに腕を振るいました。
建て主にとっても棟の高さや意匠は重要で、
昔は棟の瓦の積み方でそれぞれの家が個性を競い合っていたものです。
「隣が3枚積んでいるから、ウチは5枚にしてくれ」といった感じで建て主が要望したり、
とくに要望がなければ、瓦職人が家の格式から判断して
それに見合うような積み方をしてあげたり。
ベテランの職人さんにうかがうと、昔はいろいろなこだわりがあったようです。
棟の飾り(意匠:デザイン)にはさまざまありますが、この積み方は「輪違い」といいます。
半円形の瓦を上下に互い違いに積み上げたもので、とてもグラフィカルなデザインです。

輪違い。正確には分かりませんが、全体の雰囲気から推測しておそらく明治時代以降の土蔵かと思われます
よく見ると、瓦には苔が付いていたり、上の輪違い瓦には白い漆喰が残っていたりします。
下の輪違い瓦は漆喰が剥がれたのでしょうか?
過去に雑に補修したような雰囲気が漂っていますね。
あ、平瓦の上には剥がれた漆喰がボロボロと落ちています。
雨漏りがあったかどうかはお聞きしませんでしたが、瓦屋根の耐久性がどれくらいのものか、
どの部分が傷んでくるのか、とてもよく分かる事例です。
古民家を改修するとき、このような趣きのある瓦屋根をどうすべきか?
これも計画時の争点のひとつになります。
次回以降、瓦屋根の改修時に考えるべきポイントを解説してみたいと思います。