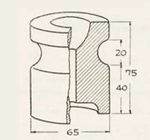危ない瓦の見分け方、その2です。
平瓦と棟の取り合い部分を「面戸」〈めんど〉といいますが、
ここは通常、葺き土を詰めて表面に漆喰を塗るか、葺き土の代わりに南蛮漆喰などを
塗り込んで仕上げます。
その塗り込んだ漆喰などが風雨にさらされたり、
地震や風などの力を受けて徐々に剥がれたり、崩れたりすると、
そこから雨漏りが発生する危険が高まります。
この写真は、「風切丸」〈かぜきりまる〉という丸瓦と平瓦との取り合い部分を
撮影したものです。
ごらんのように、もともと塗り込んでいた南蛮漆喰が崩れ始めています。
これは危険な印なので、早めに補修したほうがよさそうです。
.jpg)
南部漆喰の崩壊。関係ないですけど「風切丸」ってネーミングは絶品ですよね。建築用語では「フライング・バットレス」と双璧をなす切れ味のよさです
同じ崩壊系、破損系ということであれば瓦自体の破損も大問題です。
これは素人の方でも見れば分かるやばさです。
瓦の表面がひび割れている程度ならまだましですが、ひびが下まで貫通しているようだと
そこから雨水が直に下地に達しますので、即雨漏りにつながります。
この写真のように瓦が欠落しているような破損は論外ですね。
.jpg)
瓦が割れる原因は、意外にも自分自身だったりします。棟の一部や上部にある何かが外れて落ちてきてその衝撃で瓦が割れることがあります
瓦に問題が見つかれば、「さあ補修しなくては」ということになりますが、
そのときコーキングに頼りすぎると、却ってそれが雨漏りの引き金を引くことがあります。
瓦と瓦の重ね部分にはもともと若干の隙間があります。
隙間があることで少量の水が入ることもありますが、
逆にその隙間から水を外へ逃がす構造になっているのです。
瓦職人さんは「正しい隙間」を分かっていますが、
瓦に不慣れなリフォーム業者が、補修の際、自身の技術力不足を補うために
コーキングに頼ってしまうと、そのせいで却って出ていく水をせき止めることになります。
.jpg)
瓦のコーキング。平瓦の丸く盛り上がっている部分に白っぽいコーキングが数センチ打ってあります
緊急を要する補修の際、部分的なコーキングで難を逃れることはあるかもしれませんが、
全面的なコーキングは完全にNGです。