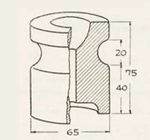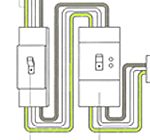古民家と聞くと、誰しもぱっとイメージする外観があるかと思いますが、
屋根についていえば、「瓦葺き」か「茅葺き」が大方のイメージではないでしょうか。

茅葺き屋根。瓦と決定的に違うのはなんといってもその厚みです。この尋常ではない厚みが建物を雨から守ってくれるのです
現代の建物と古民家は、使用される建築材料がある時期を境にがらっと変わりますが、
瓦は現代の建物でもいまだに使われ続けているという、ちょっと特異なポジションを
確立しています。
昔に比べれば数こそ少なくなっていますが、瓦はまだまだ現役の屋根仕上げ材なのです。
ある瓦職人さん曰く、
「むしろ瓦以外の仕上げのほうが一時的な流行で、本物が分かる人はきっと
また瓦に戻ってくると思うよ」
自信たっぷりにおっしゃっておりました。
本物かどうかはさておき、地域によっては瓦以外の仕上げにすると
「家としてナメられる」という妙なドレスコードがあったりして、
いまでも「きちんとした」お宅では、瓦以外の屋根仕上げは認められないという
雰囲気が色濃く漂っております。
さて、そんな瓦屋根を古民家改修のときどうするか?
古民家っぽさを残すなら瓦は当然残したいわけですが、
そのまま使い続けられるかどうかはやはりケースバイケースです。
現場でどういう判断をしているかといえば、
まず念頭にあるのはコストです。
ローコストな改修を優先するのであれば、
古い瓦をそのまま再利用するのも選択肢のひとつです。
ただし、現時点で雨漏りをしていないこと。
「現時点で」というのが重要で、「過去」に雨漏りしていた様子がうかがえても、
いま現在きちんと補修されていて雨漏りがなければ、引き続き使用可能と判断します。
室内の天井や壁など、過去に雨漏りしていた跡は古民家を調査するとよく見つかるんです。
でも、補修されていればOK。
そういうことです。

明治45年(1912年)に建てられた古民家の屋根瓦。調査時点で瓦は当時のまま、葺き替えなどはされていませんでした。部分的に雨漏りの補修をしていた可能性はありますが、大部分は100年以上そのままです
調査の結果、もし屋根からの雨漏りが認められれば、
もちろんそのまま使うわけにはいきません。
状況にもよりますが、すべての瓦を葺き替えるか、部分的な補修で済ますかを検討します。
雨漏りは屋根だけでなく、壁や天井、柱梁などその他部分の腐朽も疑われますので、
古民家にかぎらず建物にとって本当に大敵なんです。
いずれにせよ専門家による調査が不可欠でしょう。
一般の方は、間違っても瓦の上に登らないように。
古い瓦は上に乗った瞬間、割れることがよくあります。
ちなみに、
外壁なども含めた大掛かりな改修が必要で、外足場を設置しなければならない場合には、
先々のことを考慮して瓦も一緒に葺き替える、または金属板などの屋根に葺き替える、
ということがよくあります。
耐震性やメンテナンス性を考えると、葺き替えるなら金属板がいいかなという気持ちに
傾きますが、家というのは屋根の仕上げが変わったとたん、
印象ががらっと変わります。
なかなか悩ましいところです。
次回は、「それでも自分で屋根を調べたい」という方に、
屋根を下から見たり、2階から1階の屋根を見たりして、
瓦の上に登らずに瓦を調べる方法をお話しします。