前回、断熱材には目安となる断熱性能の基準があり、
過去に何度も基準が強化されてきた歴史をお話ししました。
ただ、この基準は、
住宅の場合、基準を満たさないと建てられないといった「義務」ではなく、
基準を満たすことが推奨されるという、建築主に対する「努力義務」です。
法律上、断熱は強制ではないので、
省エネ法ができた1980年代以降の新築住宅でも
寒冷地を除く比較的温暖な地方では、相変わらず断熱材が入っていない、
あるいは薄い断熱材しか入っていないといった、断熱性能の低い住宅が
建設され続けました。
しかし、2015年に温暖化対策の新しい枠組みとして「パリ協定」が採択され、
省エネルギー対策がより一層求められるなどしたことから、
国はついに、2020年からは省エネ基準の適合を「義務化する!」と息巻きました。
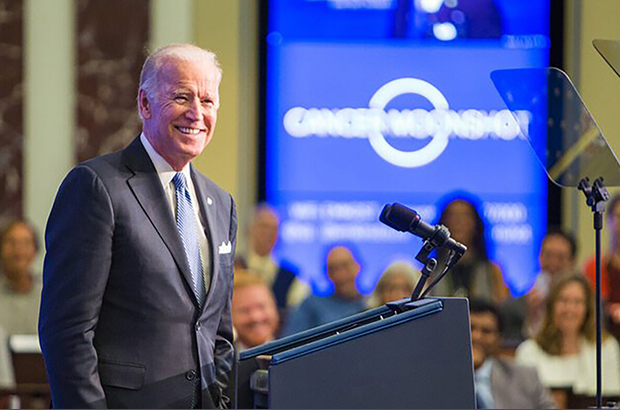
バイデン政権はパリ協定への復帰を決めましたね。出典:Earth Org.
ぜったい断熱しろ!というわけです。
これからは断熱性能を満たしていない家は新築できないと盛んにアナウンスしました。
これに震え上がった工務店はたくさんあったと思います。
とくに昔ながらの大工さんが昔ながらのやり方でつくっているような
工務店は、いまだにラフな断熱施工しか行なっていませんので、
義務化と言われても、何をどうすればよいのか分からない人がたくさんいます。
さて、この改正はどうなるのかなと思っていましたが、
2020の義務化は諸々の事情で見送られ、代わりに2021年4月(もうすぐですね)
からは、建築士が住宅(300㎡未満:約96坪)を設計する際に、建築主に対して
省エネ基準への適否を説明することが義務づけられました。
断熱が義務化されたのではなく、省エネ基準を満たしているかど
「説明をする」ことが義務化されたわけです。

義務付けられたのは「説明すること」
説明の義務化ですから、誤解を恐れずに言えば、
省エネ基準を満たしていなくても住宅は建てられます。
その場合は、どうすれば基準に適合できるのか説明しなければなりませんが、
そもそも建築主が「省エネ性能の評価や適合の説明は不要です」と言えば、
建築士からの説明は行わなくてもよいのです。
たとえば、
「夏しか使わない別荘なので、断熱材を入れなくてもいいですよ。
その分建築費が安くなるほうがよいので」
と建築主が言えば、建築士は説明をしませんし断熱材なしの住宅でも
建てられます。
実際にはないかもしれませんが、理論上はあり得ます。
そんなわけで、
新築の住宅に断熱材を入れる入れないといった規制は、
建築主の「努力義務」のまま変わりませんが、
建築士による説明義務化により、今後は
これから建てる住宅はどの程度省エネルギーになるのか、
あるいは基準を満たしているのかいないのかといった省エネ計算が
必須となったのです。
















